■0439・2025年4月13日-18日・小笠原5泊6日-08

ご訪問下さいまして、誠にありがとうございます。
乗り物系・温泉・登山などの旅と食事系のブログ、シクタン.comと申します。
東京から南へ1,000km!
小笠原諸島父島にやって来ました。
本記事は、小笠原ビジターを見学するのですが、筆者個人の趣味が優先されて、大半が小笠原航路関係の内容になってしまいました。
※記事中の価格等は、2025年4月現在のものです。
小笠原父島.大村/清瀬地区周辺をぶらぶら散策 (観光編)

東京から南へ1,000km!
小笠原諸島/父島へやって来ました。
旅の3日目は天候が良くないので、島の中心となる大村地区周辺をぶらぶらすることして‥
大村/清瀬地区散策の記事は、☝コチラ。
ご覧頂けましたら幸いです。
小笠原ビジターセンター

小笠原ビジターセンターにやって来ました。
小笠原の歴史や文化などを紹介する見学スポットです。
入ってみましょう。
小笠原ビジターセンター (東京都小笠原支庁)

中に入ると‥
小笠原の伝統的な船、アウトリガーカヌーが展示されています。
ビジターセンターでは、小笠原諸島が海洋島として誕生してからの歴史文化系展示。
貴重な自然、珍しい動植物やクジラ・イルカ情報などについて、自然科学系展示。
自然の保護・保全活動やエコツーリズムの取り組みなども紹介。
さらに、小笠原の自然や歴史を幅広く紹介するため、さまざまな企画展示や講演会、体験プログラム、自然観察会などを開催しています。

入島人数が掲示されていました。
我々の乗って来たおがさわら丸乗船人数は448名。
定員894名なので、約半分ですね。

=図書コーナー=
小笠原に関する書籍がたくさんあります。
ここだけでも一日いられそう。
小笠原の歴史年表

小笠原の歴史が紹介されています。
■年表1 (1543年~1864年)
今から482年前の1543年(天文12年)、スペイン船/サンファン号が火山列島(硫黄島)を発見し命名する。
ここからこの年表は始まっています。
▼
小笠原貞頼が1593年(天正20年)に3つの島を発見し、父島・母島・兄島と名付けたことと子孫の貞任が幕府に領有権を求めるのですが、定かではないことと奉行所の調査で貞任は詐欺罪となり江戸から重追放となってしまったとか。
▼
1853年(嘉永6年)、アメリカ東インド艦隊司令官/ペリーが黒船2隻で来航。
▼
1862年(文久元年)、咸臨丸を小笠原に派遣し、測量調査を行って父島/母島の地名が決定。
この時、ジョン万次郎が先住者の保護とここが日本領である事を通訳したとされています。
へぇー
これは勉強になりますね。

■年表2 (1875年~1946年)
1875年(明治8年)、小笠原諸島が英国との領有権問題が生じ、日本政府の調査団を乗せた明治丸を派遣し、翌1876年(明治9年)、小笠原の日本統治を各国に欧米各国に通告し日本の領有権が確定。
郵船三菱会社が小笠原航路を開拓します。
▼
1927年(昭和2年)、昭和天皇が戦艦山城で父島/母島を行啓。
▼
1945年(昭和20年)、小笠原も米軍の空襲が激化し終戦となり。米国領となる。
明治時代に日本の領有となった小笠原ですが、敗戦によって米国統治となってしまうとは‥

■年表3 (1875年~2018年)
米国統治下~返還、現在までの小笠原の様子を展示。
2011年(平成23年)、小笠原諸島がユネスコ世界自然遺産に登録。
返還後の小笠原航路の歴史も記されていました。

1965年(昭和40年)
米国統治下の時代、初代南極観測船/宗谷で小笠原へ墓参に行ったとされています。
へぇー
波乱万丈な船生を送った宗谷ですが、小笠原にも行ったのですね。
私事で恐縮ですが、今回の小笠原旅にあたり小笠原海運本社へ出向き、ついでに宗谷を見学しました。
初代南極観測船/宗谷の記事は、☝コチラ。
ご覧頂けましたら幸いです。

1968年(昭和43年)
4月に米国との間で小笠原諸島返還協定の調印式が挙行。
6月26日の正午、米軍司令部前にて小笠原諸島返還式が行われ、小笠原の青空に日の丸が蘇りました。
バンザーイ!
小笠原航路の歴史

さて、こちらは小笠原航路の歴史展示コーナー。
小笠原と人とを結びつけた歴代の船舶についてパネルと模型が展示されています。
船好きの筆者にとってこれは必見。
見てみましょう。
※小笠原航路の歴史については、ビジターセンター展示に関連項目を加筆しております。

まずは、小笠原航路の成り立ちと概要です。
小笠原航路は、1876年(明治9年)12月に郵便汽船三菱会社(現.日本郵船)が開拓したところから始まっています。
咸臨丸


■咸臨丸 (300トン)
1857年(安政4年)3月建造。
オランダのキンテルダルク造船所で建造された江戸幕府の洋式軍艦。
今から168年前の1862年(文久元年)1月、幕府の小笠原調査の目的で派遣されました。
兵庫丸

■兵庫丸 (1,411トン)
1874年(明治7年)英国サンダーランド造船所で建造。
明治政府が香港において購入した外国船13隻がのうちの1隻で、三菱汽船会社(後の郵便汽船三菱会社)に無償下付され、小笠原航路の主船として就航しました。
芝園丸


■芝園丸 (1,934トン)
日本郵船が中国航路用に建造された芝罘丸(チーフー丸)が兵庫丸の後継船として小笠原航路に就航。
1935年(昭和10年)、芝園丸と改名されました。
1940年(昭和15年)、東京と小笠原を結ぶ定期航路は、この日本郵船/芝園丸が年間26便を運航。
父島まで54時間を要し、そのうち6便は硫黄島まで延航され、芝園丸は戦前の小笠原航路を代表する貨客船でした。
戦況が悪化すると、緊急疎開者輸送.第1/2/5/8次便として計4便運航。
1945年(昭和20年1月)、芝園丸は小笠原から東京へ向かう途中に鳥島沖で撃沈され、小笠原航路は廃止のやむなきにいたります。
筑後丸

■筑後丸 (2,578トン)
1970年(明治40年)6月25日.英国D&Wヘンダーソン造船所で竣工され、上海航路に就航。
上海航路就航時代の大正10年3月28日、作家の芥川龍之介氏が門司→上海で乗船しました。
1920年(大正9年)、第一次世界大戦でドイツが敗れ、ドイツ領だった南洋群島が日本の委託統治領となった事から父島経由サイパン航路が開設。
姉妹船/筑前丸と共に小笠原/サイパン航路を担った一隻です。
東京/横浜から父島まで3泊4日を要しました。
黒潮丸


■黒潮丸 (496トン)
伊豆諸島航路を運航する東海汽船㈱所有の船舶、黒潮丸。
戦後の物資ががない時代に、東京-八丈島航路に就航船として建造された貨客船です。
小笠原海運㈱が設立される以前は小笠原へのアクセスがなかった為、東京都が傭船し、都営船として、月1~2航海のスケジュールで運航。
当時の所要時間は47時間だったそうです。

小笠原航路に就航したこれまでの船舶一覧を見ると‥
芝園丸が2,000トン級だったのに対し、黒潮丸は496トン!と、小さくなってしまいました。
図を見ると、大きさの違いが一目瞭然ですね。
黒潮丸は、今のははじま丸ほどの小さい船でしたが、グアム島のハイスクール在学中の島の生徒が黒潮丸に乗って東京へ修学旅行に行き、大きなニュースになったそうです。
椿丸

■椿丸 (1,016トン)
椿丸は、関西汽船/鹿児島十島航路に就航していた第一照国丸を東海汽船が購入した船です。
黒潮丸と同様、東海汽船から東京都が傭船し、東京都営船として小笠原航路を運航します。
1969年(昭和44年)、東海汽船と日本郵船の折半出資による小笠原海運株式会社が創業。
小笠原海運創業後も暫くは東京都への傭船が続き、昭和47年3月まで都営船として運航。
1972年(昭和47年)4月4日、これまで東京都が傭船していた椿丸を小笠原海運が東海汽船から定期傭船をし、定期運航が始まりました。
所要時間は黒潮丸より3時間短縮されて、44時間になったそうです。
父島丸


■父島丸 (2,616トン)
小笠原航路定期運航開始から1年‥
小笠原海運は、関西汽船.沖縄航路に就航していた浮島丸(昭和35年3月竣工)を購入。
父島丸と改称し、1973年(昭和48年)~1979年(昭和54年)の6年間活躍します。
所要時間は椿丸より6時間短縮され、38時間(2泊3日)となりました。
しかし、時間通りに着くのは稀だったとか。
初代.おがさわら丸


■初代.おがさわら丸 (3,553トン)
中古船で頑張ってきた小笠原海運ですが、いよいよ小笠原航路専用の新造船が就航します。
太平洋の外洋でも航海速力20.7ノット(時速約38キロ)を維持する為、強力なエンジンを搭載。
父島丸で38時間(2泊3日)だった所要時間は、28時間(1泊2日)と大幅に短縮!
海が荒れても揺れないようにと、フィンスタビライザー(横揺防止装置)を装備。
当時としては革新的な船で、1979年(昭和54年)~1997年(平成)の18年間活躍しました。
後のおがさわら丸の基礎となっています。
引退後はフィリピンのスルピシオラインズ社に売却され、Princess of the Caribbeanに改名。
セブ航路で活躍後、中国で解体されました。
初代.ははじま丸
おがさわら丸と切っても切れない関係にあるのが、母島航路/ははじま丸です。
父島-母島航路は伊豆諸島開発と言う海運会社が運航しております。

■初代.ははじま丸 (302トン)
これまで貨物船を改造した貨客船で運航していた母島航路に初の新造船として、ははじま丸が下田船渠(静岡県下田市)で建造され、1979年(昭和54年)~1991年(平成3年)に就航しました。。
1993年(平成3年)に2代目が就航すると一線を退き、第2ははじま丸に改名。
ゆり丸が就航するまで予備船として活躍しました。
2代目.おがさわら丸


■2代目.おがさわら丸 (6,700トン)
小笠原航路にも船舶大型化の時代がやって来ます。
初代の後継船として、三菱重工業下関造船所にて1997年(平成9年)2月20日竣工。
3,553トンの初代から2代目は6,700トンと船舶大型化が実現!
13,500馬力のハイパワーディーゼルエンジン2基搭載した最速の内航貨客船としてデビューし、東京-父島を25時間30分に短縮します。
1997年~2016年の小笠原航路で活躍した19年間で竹芝と父島を1,195往復・距離にして約240万km・地球60周もの距離を航海し、頑張ってくれました。
老朽化に伴い、2016年(平成28年)6月を持ってバトンを3代目に託し引退。
その後、ニウエ船籍のOGASAに改名され、船舶解体所が多い船の墓場を呼ばれるインドのアランへ向かった事から解体がささやかれましたが、インドのAngria Cruise 社が購入し、クルーズ船/ANGRIYAに生まれ変わり、ムンバイ-ゴア航路に就航したそうです。
2代目.ははじま丸

■2代目ははじま丸 (490トン)
初代の後継船として、三菱重工業下関造船所で1991年(平成3年)5月31日に竣工。
父島-母島を2時間10分で結び、1991年(平成3年)から25年間、母島の顔として運航。
2016年(平成28年)7月、3代目の就航によって2代目おがさわら丸と共に小笠原の海から去りました。。
引退後はソロモン諸島で活躍しているとの事です。
スーパーライナー オガサワラ


■スーパーライナーオガサワラ (14,500トン)
幻の定期船で終わったスーパーライナーオガサワラ。
旧運輸省の主導で完成した大型高速船です。
2代目おがさわら丸が就航中で東京-父島を25時間20分で結んでいたところを16時間に短縮するスピードを売りに、2005年11月に就航予定だったのですが、燃油高騰により国や都は支援撤退を表明。
年間20億円の赤字が見込まれることから、運航を行う小笠原海運は支援がないと会社が半年で倒産してしまうと、就航直前の2005年6月に就航は見送られました。
多額の税金を投入して建造された船でしたが、船客を乗せることなく解体されました。
3代目.おがさわら丸


■3代目.おがさわら丸 (11,035トン)
2代目の後継船として、三菱重工業下関造船所で建造され、2016年(平成28年)7月2日に就航。
2025年現在、現行のおがさわら丸です。
2代目おがさわら丸より1.6倍大型化され、1万トン級になったおがさわら丸。
離島航路最大級の定期船で、所要時間も24時間に短縮されました。
おがさわら丸の記事は、☝コチラ。
ご覧頂けましたら幸いです。
おがさわら丸/3代目と2代目の比較

2代目の引退と、3代目の初就航を目前に、新旧のおがさわら丸が父島沖で反航。
引退する2代目が「あとは頼んだよ」と、3代目に語りかけているようにみえます。
もう二度と見ることはできない光景‥
小笠原の歴史的瞬間です。

おがさわら丸/3代目と2代目の比較。
3代目おがさわら丸は船体が大型化されたにも関わらず、エンジンは2代目と同じ出力のエンジンを搭載と非力にみえますが、新設計された可変ピッチプロペラを採用し、船首部分は垂直ステム構造を採用することで、航海中の波の抵抗を軽減させ、高速化と低燃費化を実現したのです。


船旅の基本、相部屋の2等船室。
2代目は大部屋にマットが敷かれただけで各席に仕切りがなく、寝がえりをすると隣客の寝顔が丸見え状態でした。
3代目は部屋が小分けされ、各席に仕切りが設けられています。
同じ2等でも、快適度が違うのが一目瞭然ですね。
3代目.ははじま丸

■3代目.ははじま丸 (453トン)
老朽化した2代目の後継船として、渡辺造船所(長崎市)で2016年(平成28年)6月14日に竣工。
2016年(平成28年)7月1日に就航した現行のははじま丸で、父島-母島を2時間で結びます。
2代目の490tよりわずかに総トン数が減りましたが、全長は前船比8.5m増・全幅は3m増となり、船体そのものは大きくなりました。
運航会社の伊豆諸島開発が、母島の島民から要望を参考にして建造したそうです。
第二十八共勝丸 (貨物船)
さて、小笠原航路を語る上で忘れてはならないのが、貨物船/共勝丸です。
宮城県石巻市に本社がある一般不定期航路事業の海運会社、㈱共勝丸が運航し、ガソリンやプロパンガスなどの危険物や産業廃棄物などおがさわら丸では運べない物資を運ぶ小笠原にとって縁の下の力持ちと言うべき存在です。

■第二十八共勝丸 (312トン)
㈱共勝丸本社がある宮城県石巻市の造船所、ヤマニシで1993年(平成5年)11月に竣工。
船名に第二十八とついていますが第一から続くものでなく、末広がりの縁起をかついだ船名という。
東京月島-父島-母島航路を担い、東京出航から3日目に父島に着いて1泊。
4日目は父島→母島→父島と往復し、父島1泊。
5日目に父島を出航し、7日目に東京月島に戻る合計6泊7日の航海スケジュールで運航されています。
以前は、貨物船として許される旅客営業(12名以下)を行っていましたが、2014年秋頃より休止となりました。
後継となる共勝丸の就航に伴い、2018年( 平成30年)12月に引退。
引退後は、売船された2代目ははじま丸と共にソロモン諸島で活躍しているとのことです。
共勝丸 (貨物船)
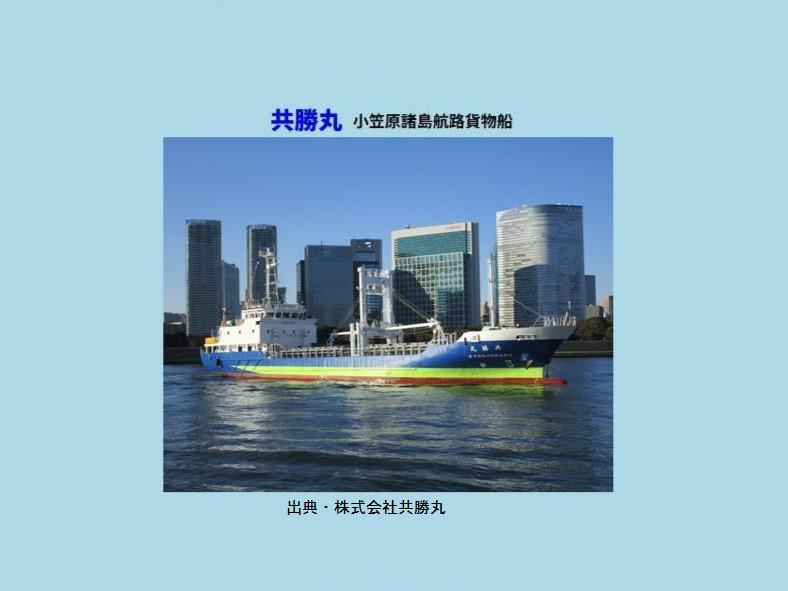
■共勝丸 (325トン)
第二十八共勝丸の後継船として、大分県の本田重工業佐伯工場で建造。
2019年(平成31年)1月に就航し、東京月島-父島-母島を往復7日間のスケジュールで月2~3航海運航。
宮城県石巻に本社がある㈱共勝丸は震災の被害を受けた事もあり厳しい経営を強いられており、新船建造費用に際し小笠原村長が自ら金融機関に協力を要請されたそう。
1万トン級のおがさわら丸と比べると小さい船ですが、共勝丸は小笠原村に貢献する重要な船であることがわかりますね。
東海汽船:すとれちあ丸 (東京-父島航路代船)
輸送手段が海路一択の小笠原。
主力となるおがさわら丸がドック入渠する時期になると、定期船は2航海(2週間以上)休航!
小笠原は外界と遮断され究極の孤島となるのですが、救世主として運航される船があるのです。

■東海汽船:すとれちあ丸 (3,078トン)
初代おがさわら丸の準姉妹船として、三菱重工業下関造船所で竣工。
初代おが丸より1年早い1978年(昭和53年)に東京-八丈島航路に就航。
おがさわら丸がドック入りした時、代船として小笠原航路に就航した事があります。
2002年(平成14年)5月に東海汽船から引退。
船体ブロック船/常秀丸として活躍後、2012年(平成24年)頃に解体されました。
東海汽船:3代目.さるびあ丸 (東京-父島航路代船)

■東海汽船:3代目.さるびあ丸 (6099トン)
2代目さるびあ丸の後継船として、三菱重工業下関造船所にて2020年(令和2年)6月5日に竣工。
通常は、東京-神津島航路に就航し、一部の日に東京-八丈島航路を担う貨客船です。
おがさわら丸ドック期間中に代船運航することを考慮していた事から、建造費の一部を小笠原村から補助を受け建造され、東京-父島航路に年に1航海を運航するようになりました。
おがさわら丸と航行性能が異なる為、東京-父島の所要時間は29時間となり、父島1泊の特別ダイヤとなります。
ちなみに2025年(令和7年)は‥
5月20日東京.10:00発→5/21父島.15:00着・5月22日父島.10:30発→5/23東京.15:30着で運航されました。
東海汽船【さるびあ丸】乗船記(東京~神津島) (4トラベル)
さるびあ丸乗船記は、☝コチラ。
ご覧頂けましたら幸いです。
ゆり丸 (母島航路代船)
母島航路を運航する伊豆諸島開発は、ははじま丸がドック入渠すると自社の代船を用意します。

■伊豆諸島開発:ゆり丸 (469トン)
第2ははじま丸の後継船として、関門造船(山口県)にて1998年(平成10年)2月に竣工した貨客船。
母島航路・青ヶ島航路を運航する伊豆諸島開発が予備船の重要性を知っていた事から、新造時から予備船として建造された稀な船で、通常は伊豆諸島への貨物便として運航されていますが、ははじま丸がドック入渠時は代船として母島航路に就航します。
他に、青ヶ島航路・神新汽船下田航路も代船運航を行い、先日、鹿児島県十島村/フェリーとしま2が機関故障による長期休航海を受け、伊豆諸島開発/あおがしま丸が代船運航を行いましたが、このゆり丸も十島村で代船運航を行った実績があります。
その運用が神出鬼没な事から ‘幻の貨客船’ と呼ばれていました。
老朽化に伴い、後継船/くろしお丸にバトンを託し、2021年( 年)10月に神新汽船代船運航をもって引退。
ベリーズ船籍のONGO NIUAと改名され、トンガ王国へ売却されました。
伊豆諸島開発「ゆり丸」乗船記 (ワンデークルーズ) (4トラベル)
ゆり丸乗船記は、☝コチラ。
ご覧頂けましたら幸いです。
くろしお丸 (母島航路代船)

■伊豆諸島開発:くろしお丸 (469トン)
ゆり丸の後継船として、渡辺造船所(長崎市)にて2022年(令和4年)1月5日に竣工。
ははじま丸の操船性能と旅客対応性能・あおがしま丸の貨物輸送性能を備え、近海海域に対応して通常は青ヶ島航路を担う誠実剛健な船を目指して建造されました。
通常は、八丈島-青ヶ島航路に就航し、ははじま丸がドック入渠時に代船として就航します。
くろしお丸の記事は、☝コチラ。
ご覧頂けましたら幸いです。
日本の東西南北四極

日本とその周辺図と日本近海海底知見図。
小笠原村は日本の端っこにある村で、画像左の地図には日本国の最端地が紹介されています。
さて、一般人レベルで行ける最端地は‥
■北‥北海道稚内市.宗谷岬。
■東‥北海道根室市.納沙布岬。
■南‥沖縄県竹富町.波照間島。
■西‥沖縄県与那国町.与那国島西崎。
~となっておりまして、小笠原村はどこにも入っていません。
ところが、真の日本国の最端地となると話しが変わってくるのです。
詳しく見てみましょう。

最北端‥択捉島。
国としては、択捉島は我が国固有の領土と言う考えなので、最北端は択捉島になります。
民間人が立ち入りできる最北端は、稚内の宗谷岬となります。

最東端‥南鳥島。
ここは東京都小笠原村です。
しかし、小笠原村内と言っても南鳥島は父島から1,300km!
東京から直線で奄美大島(1,262km)に相当する距離が離れています。

最南端‥沖ノ鳥島。
こちらも東京都小笠原村。
父島から910km南にある珊瑚の島です。

最西端‥与那国島。
本当の意味で民間人が行ける真の最端地は、沖縄県の与那国島だけです。
石垣島からフェリー又は那覇or石垣島から飛行機で行けます。
天気がいいと台湾が見えるそうです。
こちらにも行ってみたいですね。

我が国の最端地が2か所もある小笠原村。
村内の最端地を調べてみると‥
・北‥北之島。
・東‥南鳥島。
・南/西‥沖ノ鳥島。
小笠原村内で見ると、沖ノ鳥島は南と西両方の最端地となりました。
同じ村内と言っても、一般人レベルで行ける最端地はありませんね。
一般居住者がいるのは父島と母島のみですが、30あまりの島々から成る小笠原村は海洋面積を含めるととてつもなく広い村なのです。
〈 関連リンクまとめ〉
・小笠原ビジターセンター (東京都小笠原支庁)
・小笠原海運
・伊豆諸島開発
・東海汽船
・神新汽船
・東海汽船【さるびあ丸】乗船記(東京~神津島) (4トラベル)
・伊豆諸島開発「ゆり丸」乗船記 (ワンデークルーズ) (4トラベル)
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【散策/離島】小笠原父島.大村/清瀬地区周辺をぶらぶら散策 (観光編)
【船旅/散策】船の科学館・初代南極観測船/宗谷 (東京お台場)
【船旅】小笠原海運/おがさわら丸(東京→父島) 往路前編
ご覧下さいまして誠にありがとうございました。



















